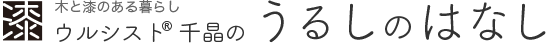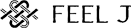『輪島キリモト』のはなし
工房へ

輪島を訪れるのは5度目。
能登は雨が多いらしいのですが、私が来る時はいつも晴れ。
この日も夏の太陽がまぶしい朝でした。
自転車を借りて街中から10分ほど走らせます。地元の方は暑い暑いと言っていましたが、東京に比べたら風が爽やかだから苦になりません。
右には青い海が見え隠れし、左には草木の緑が広がります。
黒い板塀に黒い瓦の能登独特の家並を眺めながら進むと、やがて工房というよりは工場(こうば)といった外観風情の「輪島キリモト・輪島工房」に到着しました。

「朴木地屋・桐本木工所」という歴史
桐本泰一さんは、輪島にて木と漆の仕事に携わってきた桐本家の七代目。

桐本家は江戸後期から200年以上、石川県の輪島の地で木と漆の仕事を引き継いできました。輪島塗は元来分業制で成り立っており、商品プロデュースと販売を担う塗師屋が、木地・下地・塗り・加飾など、それぞれの専門の職人に仕事を発注します。
桐本家が繊細な木工 ‘刳りもの’ を専門とする朴木地屋に転業したのは昭和初期。桐本泰一さんの祖父でした。現在は六代目俊兵衛氏の死去により、朴木地屋である「桐本木工所」を昇華させて商号を「輪島キリモト」へ改称。暮らしを応援するオリジナルブランドの漆器を次々に生み出しています。
「輪島キリモト」の挑戦
今から20年以上前のこと。バブルがはじけ、平成3年にピークを迎えた輪島塗業界の売り上げにも陰りが見えていました。ある日、若き桐本泰一さんがある下地作業をしていた漆塗職人と話します。
「蒔地の下地を前面に出すことはできるんかな?」

この話を聞いた瞬間、私の脳裏にある人の名前がよぎりました…。
バーナード・リーチ!
さかのぼること47年前の1971年、日本の民藝運動の立役者バーナード・リーチが輪島を訪れました。ある工房で下地段階のお椀を見て言います。「これで完成しているじゃないか。」
ときは高度経済成長期。多くの名工を輩出し、商社や百貨店によって大々的に売り込まれていった輪島塗はその名声をほしいままにしていました。100を超える工程、ふんだんに使われる漆液、塵の一点も刷毛目の一筋も残らない滑らかな仕上がり、金銀で施される豪華な加飾。
匠の技と贅を尽くした漆器を手掛ける誇り高き職人たちにリーチの言葉はすぐには響きませんでした。珪藻土を混ぜた漆の荒い下地肌。下地のままでは、食べ物の色も臭いもついてしまう。何をどう見たらこれで完成なのか。
それでもその言葉は輪島に大きな足跡を残していきました。
リーチの言葉を直接聞いた沈金の名手、故 角偉三郎(かどいさぶろう)氏は、次第に不完全なものが持つ美に気づき、のちに隣町・柳田村の雑器、合鹿椀(ごうろくわん)の魅力にとらわれていきます。
時を経て約30年前の1996年頃、桐本さんは下地肌を不完全なものではなく、完全なるものへと仕上げるために探究を開始します。3年の月日をかけて、ついに独自技法「蒔地(まきじ)」を編み出しました。下地に使われる地の粉を表層部にも蒔いて、さらに漆を塗り重ねることによって、独特のマットな漆肌と金属のカトラリーにも負けない丈夫さを実現させました。
開発当初は輪島では大不評だったそうです。分業が基本の輪島において朴木地屋が新たな漆器を生み出すこと自体が異例であったし、見たこともない蒔地の肌は「汚い」とまで言われ、非難されたこともあったといいます。今では輪島キリモトを代表する商品のひとつであり、TVで取り上げられたこともあって輪島内外から注目される技法として認知されています。

その後、2008年(平成20年)、輪島キリモトには「千すじ」という商品が仲間入りします。まさにバーナード・リーチが見た美を具現化したもの。地の粉の肌に美しい筋を残す刷毛目。落ち着いた深みのある色はどんな料理をも引き立てる。
輪島キリモトの「蒔地」も「千すじ」も、決してコストカットのために上塗りを省いたものではありません。手間はかえって増えているかもしれない。使いやすく且つ美しくあるために桐本さんが年月をかけて生み出した漆の新しいデザインでした。
「デザインは今の暮らしをもっと気持ちよく便利にするためのもの」桐本さんは言います。
家業に入る前に大学と企業でデザインに携わり、輪島に戻ってからも常にデザインの役割を意識してモノづくりをしてきました。単にオシャレとかカッコいいとかいう要素だけではなくて、使ってこそ分かる真の良さを伝えるデザイン。漆器というモノが桐本デザインを介して暮らしに溶け込んでいきます。
朴木地屋であることはデザインを具現化するための強力な武器でもありました。たとえばスプーン。

融解した金属を型に流し込むのとは違い、木地のスプーンはどうしても人の手をかけて仕上げなくてはなりません。優美で持ちやすくて一定の強度を要するスプーンの製品化は、豊富な経験と技術を蓄積してきた工房だからこそ実現できるのです。
これからの「輪島キリモト」
常に新しい分野へと突き進む桐本さん。かつて、1995年(平成7年)、地元若手を集めて勉強会を始めています。それまで男性社会だった業界の常識を破って女性も呼び込みました。興味を持ってくれそうな人を一人一人訪ねて説得したといいます。
しかし新しいことを始めるときには反対・批判はつきものです。やはり障害は大きくて、勉強会は余り長続きしませんでした。それでも現在輪島で多くの女性たちが活躍しているのは、この活動があったからに他なりません。
熱い語り口と強い目力で様々なネットワークを築き、異業種・異素材とのコラボレーション、海外有名企業との協業にも積極的。それでも常に軸がぶれることはありません。漆と暮らすことが当たり前の輪島という土地から、暮らしに溶け込む漆器を生み出し発信しています。
さて今、その桐本さんが次に取り組もうとしているのが五感で感じる漆の魅力の数値化です。輪島で数百年続いた木と漆の産業がこれからも継承されていくためには、やはり現代にあった分かりやすい手法でのコミュニケーションが必要。そのために、「数値化」という新たな分野に産学連携でチャレンジするといいます。
私自身も漆の魅力の伝え方を模索しているのですが、それを数値化するという発想にある種の衝撃を受けました。と同時にとても嬉しくなりました。これまで多くの産地、作家の仕事を見せていただいたけれど、桐本さんほど常にエキサイティングな驚きを提供してくれる作り手はいません。
輪島の木地屋の家に生まれ、堅牢優美な「輪島塗」の真の良さを理解していたからこそ、伝統の枠を飛び出して新たなデザインを世に送りこんだパイオニア。歩んできた道は、決して平たんではなかったと思います。伝統とは革新の蓄積であるとはよくいうものの、実際に世の中に受け入れられる革新を興すことは容易なことではないのです。それを敢行してきた人だからこそ、新たなチャレンジには説得力がありました。地元輪島への愛がありました。

私が「蒔地」の皿を使い始めて7年。毎日とは言わないまでも、かなりの頻度で食卓に登場します。軽くて、持つときにも滑らなくて、料理が驚くほどに映えるのです。伝統的な輪島塗が使い込むほどに艶を増すように、蒔地の皿も少し滑らかになり色味も明るくなってきました。一方スプーンはわが家に来て3年。毎朝のヨーグルトには欠かせない存在に。
漆器は育てる器。人の暮らしとともにあるべき器。桐本さんの思惑通り、輪島キリモトの漆器は私の暮らしに気持ち良く溶け込んでいます。
別れ際、「桐本さんの写真を撮らせてください。」とお願いすると、少しはにかんだような柔らかな笑顔をこちらに向けてくださいました。

つい先ほどまで、圧倒されるほどの強い目力で、自分の仕事について熱く語っていた人とはまるで別人がそこにいて、ああこの人の魅力はこれなのだと私も自然と笑ってしまいました。
これほどまでに愛情深く、まっすぐに、溢れる熱エネルギーを放出しながら挑戦し続ける漆びとを、私は桐本さん以外に思い浮かべることができません。
訪問先: 輪島キリモト
「輪島キリモト 漆のスプーン 小」
https://www.feeljstyle.com/items/8297596